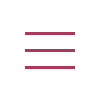エピソード
ふるさと、碓井・嘉穂。
碓井町は私が育ったところです。
「寄贈させてください」と、思いを伝えました。
想い出の作品が郷里に飾られるなんてありがたいことです。
~「絵筆とリラ」より~

ナシ畑や水田が広がるのどかな風景。実家のそばにある千手川のせせらぎにはカワセミや野鳥が羽を休め、そこでシジミやカニを捕って遊んだりと、美しい自然に囲まれて幼少期を過ごしました。3歳の頃、碓井村(現・嘉麻市)に引っ越してからは、父・鶴吉の影響で家にあった美術全集をオモチャ代わりに、ルーベンスやダビンチなどの絵を画用紙に模写してボロボロにしていたといいます。そんな思い出の地に、作品を手にしてくれた筑豊の多くの人や故郷に感謝を込めて、自ら寄贈した絵があります。4人の女性が賛美歌を歌っているような牧歌的な代表作「讃歌」。農村の風土がにおうように感じられる色調の絵には、郷里への思いがにじんでいます。


パリで見えたもの。
「きれいな建物だ」。そう思って描いたことがありました。
後で聞いたら、ルーブル美術館でした。
言葉がわからないから感動し、好奇心がわくのです
~「絵筆とリラ」より~
織田作品にはパリをテーマにしたものが多く見られます。行きたくても行けずにパリを想像して描いた独創的な作品もありましたが、1960年、船で単身フランスへ。見るものすべてが新鮮で、自然や風景、夜の女性の絵など“描きたい”という直感のまま、一心不乱に描き続ける日々。モンマルトルのサーカス小屋では、描く紙がなくなりチケットの余白にまで描いたことも…。貧乏絵描きでも心は豊かでした。憧れのパリで学んだのは、フランス人の古き良きものを大切に守り抜く頑固さ、そして何かを発見しようとする精神。同時に「織田の絵は日本人だから描ける絵」=“まねでない、個性のある絵”として、日本やフランスで認められ始めたのもこの頃からでした。

リラの傍らで。
リラは「いま売れなくても平気。三十年くらいたったら売れるのよ」と、よく山盛りのいわしを買ってきて切り盛りしてくれました。
~「絵筆とリラ」より~

誰もが生きるのに精一杯だった戦後、初めての二科展。そんな時代だからこそ夢のある絵をと、モダンな衣装を着た女性を描いた大作「黒装」。その白と黒の力強いタッチがリラさんを惹きつけ、ふたりは出会いました。結婚後、アトリエを兼ねたバラックの住まいを自分達で手作りし、自らは絵筆を取ることなく夫と子ども達を支え続けたリラ夫人。物不足の時代、一度描いたキャンバスを水につけて絵の具をはがしたり、洋服の芯地を畳針で縫い合わせてキャンバス代わりにしたり、幾つかの作品には今もその名残が見られます。暮らしは質素でも、常におおらかな愛情とうるおいのあった日々。リラさんは今なお永遠に、彼の描く絵の中に生き続けています。

画家、織田廣喜。
いい意味で、うそをついた絵のほうがいい。
キャンパスの上では自由。
楽しんで描こう。自分が楽しければ人も楽しいのです。
~「絵筆とリラ」より~

幼い頃から絶えず絵筆を握っていた織田画伯。緑の木は黄色に、ワラ小積みは茶色に、空の色は黄色にといった具合に、色を自身の好きな色に調和させ、電信柱など描きたくないものは画用紙から無意識に消してしまっていた少年でした。

また、多くの作品のモチーフとなっている国籍不明の女性たちについて、彼はいいます。「題材そのものを見て描いてもつまらない。石ころを見ても天井を見てもモデルに見えるように想像力を働かせ、その物に在る魂を描きたい」。母・マサノさんや夫人のリラさんの姿が、作品のイメージとして重なって見えるのもそのせいでしょう。夢を膨らませて、自由に楽しんで描く。それが画家・織田廣喜の絵です。